多摩川
今、身近な場所多摩川水系で非常に楽しい釣りを展開しています。
つい最近までは家族で出かけていましたが、息子たちが成長するに連れ、部活や、友人たちとの遊びが多くなったため、なかなか一緒に行ってくれなくなりました。しかし川に出かけてみれば仲間はどんどん増えていきます。多摩川を愛する人は多いのです。
ナマズ釣りが好きな私の友人、T氏が、この川はアマゾンに負けない魅力がある、と「タマゾン川」と呼んだのは2008年のことです。
都市近郊でこれだけの生産力を持つ川は貴重です。魚だけではありません。周辺の樹木、鳥、野生動物たちも豊富で、人間が作り変えた多摩川がもたらす生態系といっても過言ではないでしょう。水再生センターから栄養塩たっぷりな温かい排水が流れ続けているのですから、熱帯魚が生き延びる可能性があるのは当然です。でもそんな魚は淘汰されるのが常です。
最近では熱帯魚、特にガーなど大型魚がいる川だからと、危険な川、悪の川と言う憎しみやからかいを含めて誹謗され「タマゾン川」と言われてしまうこともありますが、私たちは偉大なるタマゾン川だと思っています。
アマゾンに負けないほど豊かな川その「タマゾン川」が、マスコミの偏見、興味本位、一部の漁業者によって、熱帯魚が生息する悪いイメージ変えられてしまったことは残念です。T氏の言葉を漁協の方に伝えたことから始まってしまいました。今ではビジネス、宣伝ネタなどに利用されています。
発表もしませんでしたがタマゾン川の本当の名付け親、T氏が感じた多摩川の生産力の凄さを、みんなが知っているのです。

地元を流れる多摩川は全長138kmの川です。私の住む羽村には取水堰があり。ここで多摩川の水は半分以下になってしまいます。
しかしその下流で、平井川、秋川、浅川などの川が合流し、水道で使われた家庭水などは水再生センターで処理され再び多摩川に戻されます。その水が温かいので、冬でも魚は活発です。
この多摩川は昭和40年代、死の川と呼ばれるほど汚れたことがありましたので、再生された今でも「汚い。」というイメージがありますが、実は魚がたくさんいるのです。
上流ではサケ科魚類。中流域より下流ではコイ科の魚がフライフィッシングで楽しめます。
私は今、多摩川を良き川として見直し、フライフィッシングを楽しんでいます。そして時には高校生のフィッシングゼミなどでエサ釣りをして、小物釣りの楽しみを釣りの原点として再認識しているのです。
高温の生活処理水が多摩川の何箇所かから流れ込んでいるため、飼えなくなった熱帯魚を放流する人がいます。冬が来ると死んでしまうこともあるのですが、ごくまれに越冬する魚もいます。
流域に生活する人が400万人以上と言うこの大都会の川にはさまざまな魚たちが生息しています。上流にはイワナやヤマメもいます。特にコイ科の魚たちには処理水がもたらす栄養によって、飼料が多いため、人間の生活と密着しているといえます。加えて東京湾から溯上するアユやマルタ、特に中流域ではナマズやニゴイなど、その魚影は抜群です。
 ニゴイがフライで釣れました。
ニゴイがフライで釣れました。
 こんにちは。私がタマゾン川の主、ナマズです。
こんにちは。私がタマゾン川の主、ナマズです。
多摩川は本当に良い川です。遊びに行くには駐車場が少なすぎることだけが気になりますが、川のどこへ行くにも最寄の駅から徒歩15分以内、土手道にはバスも走ってます。

オイカワなどのコイ科小物はフライロッド#0~2番ぐらいが面白いです。
コイ釣り(コイのフライフィッシング)

西山徹さんが教えてくれた。
1988年の暮れ。故、西山徹さんから「奥山クン、来年の初釣りは多摩川でコイ釣りをしようよ。」と誘われました。
私は「え、コイですか?」と怪訝に答えたのを覚えています。正直に申し上げまして、コイはドローンとしたあまりキレイな水ではない場所で、ネリエサで釣る退屈な釣りだと思っていましたから。
しかし西山さんは「今までの常識と違うから、、、、フライで釣るんだぜ。6番のタックルを持っておいでよ。」
そして1989年1月2日、西山さんは私を調布市周辺に案内してくれました。現在の稲城大橋のちょっと下流ですが、その当時、橋はありませんでした。
そこではコイが川底をつついたり、水面にパクパクして浮いている何かを捕食していました。「こんなにいるの?」と驚きました。しかも川の流れは想像していたよりもきれいでした。
西山さんはニヤッと笑い、
「な、すごいだろ?」と、
そしてこれをドライフライで釣るんだよ。と教えてくれたのです。
私は釣り方がわからなかったので、まずは師匠の釣るのを見ていました。
フライはエルクヘアカディス。上流から、斜め下流にキャストし、フライ先行で流していきます。
何回かするとコイがパクッとそのフライを吸い込みました。
バシッとアワセが決まり、バシャっとその場で水しぶきをあげ、そのコイは走り始め、キュイーンと(当時はそう聞こえた)リールを唸らせ(逆転している)、バッキングラインまで引き出して走ったのです。
驚かないわけがありません。淡水魚でバッキングラインを引き出していくなんて、当時の私の常識では「アリエネー」って感じでした。魚が掛ったらフライラインは手で手繰るものだと思っていたからです。
浅瀬に引き寄せられたそのコイは55cm。
巨大に見えました。今ではもっと大きなコイも普通に釣れますが、当時はそれで十分大物だったのです。
度肝を抜かれたって言うことを痛感しました。
しかもその日、私は初挑戦でボウズ。翌週から多摩川通いが始まりました。そして多摩川の生態が徐々にわかってきました。
今でも、多摩川でコイを釣るたびに西山さんを思い出します。

家族で行くもっとも手軽な大物釣り。
 長男の魚を次男がすくう我が家の仲好しフィッシング
長男の魚を次男がすくう我が家の仲好しフィッシング
あれから25年が過ぎ、多摩川のコイ、都市近郊のコイの生態が理解できました。人間の生活と密着しているコイは特殊な生態なのです。
西山さん以外にも凄い人が出てきて、多摩川のコイをフライで釣りまくっている人は多くいます。藤田克昌さんがその代表的な人です。
氏の著書「都会のコイはフライで釣れ!」(つり人社刊)には多摩川の情報が、コイの生態がきちんと書かれています。
また藤田さんの「フライでコイを釣るというホームページは出版後の活動のすべてを記してあり、なかなか見ごたえがあります。(結構マニアックですが)
私がここでコイ釣りの解説をするよりも氏のホームページをご覧になった方がいいでしょう。
私たちは家族でコイ釣りを楽しんでいました。パンをイミテートしたフライなら釣りやすいと思います。
毎年正月、初釣りとしてキャスティング練習も兼ね、支流の浅川へ行くのですが、長男が小学4年のときには、新春第一投目で釣ったこともあります。

また次男はと言えば長男の掛けた魚をネットですくうのが大好きで、「獲る」という満足度も感じていたみたいです。
そのうち、食パンをエサに釣るのは当たり前と思うようになり、 今では長男、次男ともにコイはフライで狙うようになりました。投げ方が上手でなくても、コイが射程範囲に寄ってくるまでじっと待つ釣り方も覚えました。
家内もフライでJGFA(ジャパンゲームフィッシュ協会)公認の日本記録も釣りあげました。ただ釣りまくるだけでなく、記録認定され、釣りのギネスブックと呼ぶべき立派な本に名前が載るというのもいいものですね。
 家族でフライフィッシング
家族でフライフィッシング 2ポンドティペット(1kgテスト)で釣った4,4kgのコイ。太りすぎか?(笑)
2ポンドティペット(1kgテスト)で釣った4,4kgのコイ。太りすぎか?(笑)
 コイのフライはこんなパンフライ。
コイのフライはこんなパンフライ。
コイはリリースしています。最近では鱗にダメージが少ないラバーネットの大型は販売されるようになりましたから、それを使って、出来るだけローインパクトに扱っています。
正直に言いまして、1尾だけ扱いが悪く、死んじゃったので持ち帰って食べようと試みましたが、臭かったので諦めました。
とにかくフライで大物を釣ったことがない人は、コイを釣って練習したらいいと思います。ただしフライフィッシングですからまぐれがありません。初心者でもバシバシ釣れるほど簡単ではないですよ。練習あるのみです。
コイはハリのついたパンのニセモノが流れてくるのを知っています。(本当)
フライ先行できちんと流さなくては釣れませんので、ヤマメのライズを釣るシビアな釣りの練習にもなります。
掛からない理由はただひとつ「見破られているから」です。フライが悪いのか、アナタの技術が足りないのか、、、、、???

そして掛かったらリールを逆転させて釣る、ビッグゲームにも対応できるようになります。最近流行りのツーハンドでやれば多摩川本流の堰上の広い場所で、遠くの魚も狙えます。
晩秋にシロザケ釣りを目指す人は、それまでにコイを釣って慣れておきましょう。
 パクパクやるがなかなか食いつかない
パクパクやるがなかなか食いつかない
コイはぜひフライで


息子たちが小さかった頃は、フライだけでなく、パンを餌にして釣りました。それはそれは簡単な釣りです。ちょっと釣りをやっている人なら本当に簡単です。
本物のパンをハリに付けて流すのですから、コイがいれば間違いなく食いついてきます。まさしく「ガキの遊び」のように釣れちゃうのです。息子たちも成長するに連れてフライに切り替えました。
ですから普通の釣り人がまじめにパン釣りをやってはいけません(笑)。あくまで女性や子供(中学生ぐらいまでかな?)の領域としてそっとしてあげましょう。

 2012年は初つりを家族でやりました。これは家内の71cm。
2012年は初つりを家族でやりました。これは家内の71cm。
フライタックル
ロッド 9フィート前後の5番以上、できれば6番か7番
(ツーハンドもOK)
70cmオーバーを基準に狙うなら8番。
リール 出来ればドラグ付きのもの
ライン WFかSTのフローティング。
リーダー 0X9フィート
ティペット フロロカーボンの2号前後
リーダー&ティペットで3,5m~4mぐらい。
フライ 上記のフライ。これ以外にもいろいろと試してくださいね。
 コイ釣り用にフォアグリップを装着した6番ロッドでフィッシュオン!
コイ釣り用にフォアグリップを装着した6番ロッドでフィッシュオン!
コイは多摩川の場合、全域で遊漁対象魚になっています。
従いまして遊漁券が必要です。
大人 1000円
子供(小学生以下) 無料
年券 5000円
遊漁券を発売している場所がほとんどなく、監視員、販売員がたまに巡回していますので現場で購入することになります。
もし来なかったら、もちろんタダ。
ちなみに下流の登戸周辺はいつも監視員が来ます。
年券を買われたほうがお得です。


下流域には巨ゴイも多いです。これらはともに10kgオーバー。右の魚はJGFA公認の女子日本記録魚。ティペットは6kgクラス。立派な魚です。
ナマズ
タマゾン川と言わせる魚影の濃さ
急流に走る
多摩川にはナマズもいます。この魚、人によって好き嫌いがはっきりしています。
気持ち悪いという方もいます。
しかしタマゾン川の名前のルーツはナマズだったのですから。(最下段参照)
ナマズ釣りといえば池や沼、川の水のよどんだ場所をイメージする方が多いのではないでしょうか?しかも夜ですよね。
しかし多摩川のナマズは昼間に瀬でヒットします。東京湾から大量溯上するアユを食べているからです。そうです。友釣りをするような瀬の中でもヒットしてくるのです。
アユが泳ぐ瀬にいるナマズ。想像できますか?

サクラマス釣りのような、川スズキ釣りのようなイメージでナマズ釣り、ヒットすればドラグがジィーッ!
のた打ち回る陰気なナマズのイメージが吹き飛びます。コイ同様、この川のナマズはサケ科か?と思ってしまうほどパワフルです。

ミノーや、スプーンで狙います。BUXと言うスプーンはフロントワイドで、深く潜るのでいいそうです。いろいろ試して見ましょう。

使用タックル
ロッド ブラックバス用のミディアムアクション~ミディアムヘビー
ライトシーバスロッド
長さは6フィート(1,8m)ぐらいから9フィート(2,7m)ぐらいまで。
リール スピニングでもベイトでもOK。ナイロン3号(12ポンド)が100mぐらいあればいいです。
ダイワなら 2500番クラス
シマノなら 3000番クラス
ライン ナイロンのほうがイトさばき、クッションがいいと言う人や、PEは細いので飛距離が出る、アタリがダイレクトで面白いという人がいますが、、、、。フロロも同じ理由で。
しかし安価なナイロンで始めたらいかがでしょうか?
リーダー なくてもいいのですが、多摩川のナマズポイントにはテトラポッドや、ガレキなどが多くありますから、付けておいたほうが無難。
フロロの4号~5号をお勧めします。ラインにフロロ16ポンド(4号)以上を使う人は直結でOKですね。
ルアー 私たちは朝から夕方までのデイゲームをしますので、ナマズの人気ルアーであるジッターバグなど、トップウォータールアーは使う機会がほとんどありません。
ミノー(シンキング&フローティング&サスペンド)7~12cm
バイブレーション(ラトルなしがいいらしい)
シャッド
そしてスプーンを多用します。スプーンはBUXの9g~14gに実績が集中しています。
名人に言わせるとバス用ルアーなら何でもOK。ワームやグラブでも釣れる、というわけで、たくさん用意すると荷物になりますから、個人判断でどうぞ。
私はナマズ釣りは修行中の身、随時アップしていきます。フライでもチャレンジを繰り返しています。皆さんも一緒に挑戦しませんか?




ナマズの存在がタマゾン川のルーツ
2008年、ナマズ釣りにはまっていた私の友人が「多摩川はアマゾン川に負けないぐらい魚影が素晴らしい。特にナマズ。大都会の脇でこんな凄い魚がいるなんて」とタマゾン川とあだ名を付けました。
それが今、マスコミによって意味が捻じ曲げられ、熱帯魚が棲む異変の多い川として悪いイメージになってしまいました。私たちは名誉挽回しなくてはなりません。
 特定外来生物のオオクチバス、コクチバスも法律を守り、生きたまま移動させなければ大丈夫。
特定外来生物のオオクチバス、コクチバスも法律を守り、生きたまま移動させなければ大丈夫。
フライフィッシング

最近のチャレンジはフライフィッシングです。ルアーで釣れるのだからフライで釣れないはずがない。
しかしルアーでヒットしているのにフライはアタリもないということが何度もありました。
なぜわざわざフライで挑むのか?
それはフライフィッシングが面白いからです。
取り合えずの目標は3kgオーバーをフライロッドで釣ることです。
それは非常に太った70cmオーバーの魚体なのです。
最終目標は80cm、5kgオーバーです。タマゾンにふさわしい怪魚だと思いませんか?
ロッドはシングルでもツーハンドでも。
スティールヘッドとは色も形もかけ離れて地味な魚ですが、流速の早い場所でもヒットするので、その味わいはスティールヘッドに劣りません。
タックルはバビーンリバーのページをご覧ください。
ツーハンドならスカジットシステムで挑むことが出来ます。重くて大きいフライを投げるのが楽です。



 時にはフローティングラインでつれるほど浅場に来る。昼間でも。
時にはフローティングラインでつれるほど浅場に来る。昼間でも。 コクチバスもナマズ狙いのフライにヒット。
コクチバスもナマズ狙いのフライにヒット。
 ツーハンドのスカジットシステムでゲット。
ツーハンドのスカジットシステムでゲット。

マルタと言う魚!東京湾から多摩川に巨大魚遡上!
2ヶ月間だけのシーズンを楽しみましょう
「雛祭り」から「子供の日」までの約2ヵ月間、東京湾で育った巨大魚が多摩川に遡上します。
それはまるでサケのようです。浅瀬でバシャバシャと産卵(瀬付き)するその姿をいっぺん見に来てください。
そのシーンを動画で記録しました。画質がよろしくありませんが、こちらもご覧ください
フライフィッシングマルタイン多摩川
その魚はマルタ

近年は東京湾から遡上してくるマルタの溯上が楽しみです。50cmオーバーのウグイの親分みたいなヤツがフライやルアーに掛かります。
この魚の釣りはバーチャルサーモンフィッシングと言うべきエキサイティング。
ヒットすれば時に激流を突っ走り、都会のスティールヘッドみたいです。ちゃんと紅い帯もあります。(笑)
 ライトツーハンド、スイッチロッドが活躍します。
ライトツーハンド、スイッチロッドが活躍します。
そして東京湾に下って大型化したウグイも多摩川に遡上します。まさしくウグイの親分です!!
多摩川ってスゴイ川でしょう?。一度その溯上を目撃、引きを味わったなら、感動して病みつきになることでしょう。
 次男がフライで釣ったこのマルタはなんと2kg。60cm。
次男がフライで釣ったこのマルタはなんと2kg。60cm。
 GW以降なら子供たちはサンダルで川に入っても大丈夫。
GW以降なら子供たちはサンダルで川に入っても大丈夫。
マルタのシーズンは3月上旬から始まり、5月の連休明けで終わります。(雛祭りからこどもの日まで)
初期は大型が多く、晩期は小型が多いと言われていますが、、、、。平均サイズは52cmぐらい。たまに40cmぐらいの小型や、60cmぐらいのが釣れます。2011年はすでに66cmが上がったとか、、、。
下流は調布堰の下の汽水域から、宿河原堰(登戸堰)を超え、上流は二ヶ領上河原の堰の下まで遡ってきます。私たちは電車で行きやすい登戸周辺か、二子玉川周辺へよく行きます。
コイはいつ行っても釣れますが、マルタはシーズンを外すと釣れません。たった2カ月です。お忘れなく。
瀬付きといって産卵のために魚の群れがバシャバシャとやるときは絶景です。しかしそんな時は一か所に釣り師が集中しがちです。
譲り合って、自他共楽の気持ちを持って釣りましょう。交代しながら釣っても十分釣れます。
 ロッドは何でもOK。とりあえず、釣りましょう。
ロッドは何でもOK。とりあえず、釣りましょう。
マルタとウグイ
ちなみに
マルタもウグイもコイ目コイ科の魚です。
しかし全く別の魚です。
マルタ
学名
Toriboridon brandti
英名は
Pacific redfin (パシフィックレッドフィン)
カッコイイでしょ?
ウグイ
Triborodon hakonensis
です。
ほとんど近いこの2種、ウグイは淡水魚として有名ですが、マルタは生活のほとんどを汽水、海水で過ごすため、河川型がいません。
つまり、産卵に遡上した時だけ、川で釣ることができるのです。
マルタは、東京湾以北の外洋に面してない海や、入江、運河に生息する魚で、川に滞在しません。河川には産卵のためだけに遡上します。孵化後は短期間で海へ下ります。
生息域は図鑑に寄ると北日本と言われていますが、静岡県の川や、愛知県の川で釣れたという話を聞いたこともあります。
婚姻色の黒バンドはマルタが1本、ウグイは2本、レッドバンドはマルタが1本、ウグイは3本です。たまに2本のみが濃い赤で1本は薄い場合があります。
 ウグイ。
ウグイ。 マルタ。
マルタ。
 婚姻色が薄いウグイ。
婚姻色が薄いウグイ。 マルタ ♀
マルタ ♀
 これもマルタ。色が濃いです。
濃いから♂。ウスイから♀というのはウソです。
これもマルタ。色が濃いです。
濃いから♂。ウスイから♀というのはウソです。
 これはウグイ。恐らく東京湾へ下って遡上したか、丸子橋より下流~河口あたりの汽水域でいいエサ食べて大きくなったと考えられる。
これはウグイ。恐らく東京湾へ下って遡上したか、丸子橋より下流~河口あたりの汽水域でいいエサ食べて大きくなったと考えられる。
2010年まで遡上ウグイはマルタ100尾に2~3尾と言う割合でしか釣れていませんでした。しかし2011年はまとまったウグイの遡上がありました。30尾釣って全部遡上ウグイと言うことさえあったほどです。
多摩川下流域に漁業権を持つ、川崎河川漁協の、早川弘之さんの話では、マルタの本格的な遡上が始まって10年間、こんな年は始めたです。ということ。
考えられるのは10年に一度の大量遡上なのか、あるいは今年から大量遡上が始まって、来年からもマルタに追いつくほどの勢いで繁殖が始まり、毎年こんな多量のウグイが遡上するのかと言う期待もあることです。
で、調べてみたら数年前に信濃川産のウグイを放流し始めたそうで、それが海(運河)に下って溯上しているらしいのです。恐るべし多摩川!!!
マルタと競合しないことを祈ります。
今では毎年マルタに負けないほど上っています。
マルタの舞ルタの舞


浅瀬で一面にバシャバシャやるのを瀬付きといいます。(カーニバルと呼ぶ人も)
一回始まると3日から5日ぐらい続きます。
タックル
さまざまな意見があり、名人の言うことはみんな違うので「コレ」、という決め手はありません。
また、名人であるはずの常連が、連発する初心者女性アングラーをみて「どんな仕掛けで釣ってるの?」と聞いてきたことがあるほどです。スティールヘッドと同じく、遡上魚はミステリアスなのです。
スーパー瀬付きと言って浅瀬で産卵の乱舞する時には入れ食いモードになったりしますが、数は問題ではありません。できれば快心の一発を求めてください。
1日何匹釣って幸せになるかは人によって違うのです。
地元の爺さんたちはスピニングで4~5尾釣って「もう十分」と止める人もいます。しかし、釣りまくっても止めずに場所を譲ってくれないフライマンもいます。
これから始めるアナタもぜひ上品で素敵な丸太伐採者、いやマルタアングラーになってください。

フライタックル
ロッド:8フィート以上 できれば9フィート6~8番
あるいは11フィートぐらいのスイッチロッド
ライトツーハンドなら4~6番(スペイ規格)
リール:ドラグが付いているリールでなくても対応できます。でも付いていると楽。それでもクリック音のキャイーンは素敵!
ライン:フローティング
シンクティップまたはフローティング+シンキングのポリリーダー5フィート。
リーダー:9フィート2X
ティペット:フロロカーボン10ポンド(2,5号) 50cmぐらい。
フライ なんでもOK。#6~#12
各種ウエットフライ、ウーリーバガー、ウィーリーバガー(ウィーリーでボディを巻いたフライ)、ウィッグルバガーなど。エッグフライも。
 ローヤルコーチマンウエットで釣れた。ちょっと品のあるフライセレクト。
ローヤルコーチマンウエットで釣れた。ちょっと品のあるフライセレクト。

仕掛けは3タイプ
●フローティングライン(ショットリグ)
以前はリーダーにかみつぶしオモリをフライの上50cmほどの場所に付けてやってました。しかし近年ではナマリが自然に優しくないと言う小さな配慮から、タングステンオモリをを使う人も増えています。
ウキゴムを二つ装着し、バス釣りようのネイルシンカー(0,5g、、9g、1,2g)ぐらいを挟み込むようにして止めます。
あるいは重いスイベルをオモリ代わりに使います。3連スイベルとか、3Bのシンカースイベルがスマートです。
浅く急流なのでフライだけ沈ませるためにオモリを使う。
アラスカのニジマスを釣るときのショットリグ(おもり仕掛け)と同じ。
ちょっと投げにくい。軽いラインだとロールキャストしてもオモリが浮き上がらないという難点あり。キャストの際は超ワイドループでどうぞ。危ないですから。
ツーハンドだと楽です。
 ショットリグの名手、川崎河川漁協の早川弘之さん。
ショットリグの名手、川崎河川漁協の早川弘之さん。
●フローティングライン(ウキ釣り)
リーダーに中通し式のウキ(私のお勧めはスティックボーバー)を付け、ティペットの先にサルカン(スイベル)を付け、その先にショックリーダー(ハリス)を20cmほど付ける。スイベルはNTスイベル4番(0,4g)を基準に。オモリをつけないのであれば重いものを。
スティックボーバーは中通し式の棒状ウキ(インディケーター)です。
 2連ウキは、フライが一直線に流れているのが分かりやすいのでジュニアにも釣りやすい。
2連ウキは、フライが一直線に流れているのが分かりやすいのでジュニアにも釣りやすい。
●シンクティップまたはフローティングライン+シンキングリーダー
シンキングリーダーはリオか、ビジョン、エアフロのポリリーダー・エキストラファーストシンキング5フィート。これにフロロカーボンティペットを50cm繋ぐ。
コーンやビーズヘッドなどの重いフライがいいです。
瀬に出ていないでトロ場でロールするような群れの中を釣るときはこの仕掛けが有利。
 ライトツーハンドアルトモア)でヒット。
ライトツーハンドアルトモア)でヒット。
またオモリを付けてキャストがドボン!ではフライフィッシングっぽくないからイヤ、とこだわる方はコレです。。
ルアータックル
ブラックバスのライトアクションか、トラウトの本流タックル。相手は50cm上というのを前提に。
ライン8ポンド~12ポンド(2号~3号)
ルアー
3~10gのスプーン(シングルフック)
・ダンサー、チヌーク、バックス、ミュー、管スプーンなど
3~7cmのミノー(サスペンドかシンキング)
・ラパラ3cm~5cm。月虫撃沈55mm、X55、流6cmシンキングなど
 家内は管釣りでトラウトを狙うためのルアータックルを使用し、2ポンドラインでゲット。ルアーはメガバスX55.
家内は管釣りでトラウトを狙うためのルアータックルを使用し、2ポンドラインでゲット。ルアーはメガバスX55.
5g前後のスピナー
・ブレットン、アグリア、SCスピナーなど。地元のルアーマンは結構スピナーで釣っています。侮れません。
ジグヘッド フックサイズ#2~6 1~2gぐらいでマラブーのシェニールを巻いたクラッピージグみたいなもの。
スプーンの後ろ、あるいはシンカー(オモリ)にトレーラーでフライを結んでもいいです。テキサスリグのようになります。
 バスタックルでも、エギングタックルでもなんでも流用可能。マルタロッドっていうのはたぶん発売されだろうね。
バスタックルでも、エギングタックルでもなんでも流用可能。マルタロッドっていうのはたぶん発売されだろうね。

フィッシングテクニック
マルタは遡上魚ですから、テクニックはサケなどの遡上魚と同じです。
以上です。はい、おしまい。

と言うわけにはいきませんよね。もちろん日本のサケ釣りも参照にしていただきたいのですが、
基本は川底を流すことです。
やる気満々でフライやルアーを追いかけることはまずありません。(深場にはたまにそんなヤツもいますが、、)
魚が見えているときは、口元まで流しこんでやるような気持ちで釣りましょう。
魚がたくさん見えるのに釣れないのは、
1 本当にヤル気がない。産卵のためエッチに夢中。あるいは産卵が終わって疲れ果てている。
2 ハリが魚の口元に流れていない。つまり沈んでいない。
のどちらかです。
専門用語ではボトムバンピングといいますが、川底を叩くように流していくべきです。当然、川底の石に擦れてハリ先があまくなりますから、適度なフックの交換が必要です。
ヤル気がない場合でも、時間帯によって突然ヤル気が出ます。ヤル気のある魚を探して移動するか、休憩しながら同じ群れを狙うかの選択はお任せします。
瀬付いていないときは見えないけれど、その下流の深い場所で群れていることがあります。そんな魚を狙う時はしつこく何回も投げることが肝要です。
ヒットはいろいろ
ギューンとひったくって行ったり、
コツンと来るだけだったり、
ウキ釣りならウキがシュポッ!
バシュッってアワセると
川底の石、ってことも当たり前にあります。
もしかしたら魚じゃなくてもいいから、何か感じたら空合わせ(カラアワセ)も必要です。
 中3のM美ちゃんはウキ釣りで初マルタゲット。
中3のM美ちゃんはウキ釣りで初マルタゲット。
魚が居過ぎるときは、魚の口にちゃんと掛かるフェアフックが4割、口以外に掛かるファールフックが6割ぐらいですが、特にファールフックすると結構な力で下流に突っ走ります。
この時、下流側にいる方に
「ゴメン」
「スミマセン」と声をかけて下って行きましょう。
そして魚をリリースして戻ってきたら
「ありがとうございます。」とお礼を必ず言い、もしまだ釣れていない人がいたらポイントを譲って、どうやって釣ったかなども解説し、楽しみを分かち合いましょう。
小学生レベルのマナーのお話ですが、これができない大人が何と多いことでしょう。

混んでいるときや、一か所でしか釣れていない場所に入らせていただくときも、挨拶が大切です。そこしかないからと言って、無言で回り込み、投げ込んだら、、、。
ぜひとも一声掛けましょうね。混んでるときはお互い様です。とみんな分かっているはずです。
常連はほとんど温厚な人ばかりですが、そんな人たちに「いやなヤツ」と思われたら行きづらくなると思いませんか?
多摩川下流域におけるマルタ釣りの最高のテクニックは挨拶です。
私は度々マルタ釣りの案内をブログなどでしていますが、マナーの悪いヤツが増えるから止めてくれと言われたことあるほどです。みなさんはそんなヤツにはならないでください。
取り込みとリリース
取り込み浅すぎない浅瀬に誘導して水中でフックを外すか、ラバーネットなどの魚体に優しいネットですくってください。岸に引き釣り上げるなんて言語道断ですが、浅すぎる浅瀬に誘導しても、魚が暴れて眼を打ったりして傷つきます。配慮をお願いします。
そして、蹴っ飛ばすなんていう行為は止めてください。魚に対して優しくないばかりか、好敵手に対して失礼だし、釣り人としてみっともない行為です。
笑っているアナタ、気を付けてくださいよ。
遊漁券
多摩川で釣りをするためには遊漁券が必要です。
売っている場所はありませんから、現場売りのみになります。
監視員が売りに来たら素直に支払いましょう。ただしウグイなど雑魚券は500円です。コイは1000円。
リールを使っているからと1000円要求されることもありますが、雑魚券は500円です。「私はコイ釣りをしていない。」ときちんと主張しましょう。
リールが付いているから値段が違うという設定は、私が中学生の頃からありましたが、漁業法としてはすべて竿釣りに入りますから分けることは出来ないのです。
もちろんマルタに混じるコイも狙っているのなら1000円払ってくださいよ。
年券のススメ
多摩川漁協
川崎河川漁協
多摩川の環境を良くするために漁協にその資金を少しでも提供する意味で、年券を購入することをお勧めします。
ウグイ類の雑魚券は2500円
コイもOKは 5000円
投網OKは8000円
多摩川ではコイ釣りも楽しめます。フライフィッシングする方は、できれば5000円の年券を購入するほうがいいと思います。
常連の方は漁業組合員が多いので、「年券買いました。」と言うと、もっと情報をくれるかもしれません。
マルタ情報・多摩川森林組合
![aa9bb008[1].jpg](_src/sc1542/aa9bb0085B15D.jpg)
マルタの花道
多摩川のマルタを丸太として伐採する(釣る)と言うジョークを考えた西山雅也さんのブログです。彼の丸太伐採チーム(釣り仲間)は多摩川森林組合と呼ばれています。
イラストはあの柴野邦彦さんです。
私もバッジいただきました。ブログもずっと参考にしています。
 グラスロッドやビンテージ物のフライリールなど、味のあるタックルでマルタ釣りを楽しむ西山さん。
グラスロッドやビンテージ物のフライリールなど、味のあるタックルでマルタ釣りを楽しむ西山さん。

トラウトフィッシング
 小菅川冬季ニジマスC&Rエリアにて。
小菅川冬季ニジマスC&Rエリアにて。
多摩川の上流ではイワナ・ヤマメ・ニジマスなどのトラウトフィッシングができます。
 ヤマメ。魚の撮影はできればこうして水の中で。
ヤマメ。魚の撮影はできればこうして水の中で。
 イワナ。奥多摩湖より上流の沢に多い。
イワナ。奥多摩湖より上流の沢に多い。
 ニジマス。放流魚の代表だが、引きが強くて面白い。
ニジマス。放流魚の代表だが、引きが強くて面白い。
ここには3つのタイプの釣り場があります。
本流、沢、キャッチ&リリース区間の3つと管理釣り場です。
沢には放流モノでない野生魚がまだいる可能性がありますが、基本的には成魚、あるいは稚魚放流が大きくなった魚とお考えください。
この釣りに関しては今後少しづつ書き足していきマスのでお待ちください。
キャッチ&リリース区間(C&R)

奥多摩湖にそそぐ小菅川には、イワナやヤマメが生息し、ドライフライで釣り登るスタイルのフライフィッシングが楽しめます。
しかし最下流域の奥多摩湖のバックウォーターからC&R区間があり、いつでも魚がいる環境が保たれています。
実は山梨県でのC&Rは非常に貴重なのです。
 初心者を指導するならいい場所だと思います。
初心者を指導するならいい場所だと思います。
山梨県人が聞いたら怒るかも知れませんが、30年ほど前、渓流釣りがまだまだ盛んだったころ、全国で一番マナーが悪いのは山梨県人だと言われていました。
山梨ナンバーの車が来たら気をつけろとも言われていました。
その山梨県で、C&Rが出来たことは非常に評価すべきことなのです。同じ頃相模川水系の道志川にもC&R区間ができましたが、こちらは管理しきれなくなってなくなりました。

さて小菅川のC&Rには定期的に成魚が放流されていますから、魚影も結構あります。しかし魚がいるからということで有名になっているため人も多いので、魚は結構賢くなっています。つまりたくさんいてもなかなか釣れない。
それを釣るためにあれやこれや考えながらゲームするのが面白いのです。
ここでは「こうすれば釣れる!」という釣り方はあえて解説しません。
ぜひお出かけください。ライズする魚を見て、興奮してください。どうやったら釣れるか考えてください。

ライセンスは大人800円、女性と中学生は400円、小学生以下は無料です。

釣り方はルアー&フライのみ、エサ釣りは禁止です。
写真を撮るなら浅瀬にネットを浸けたままで撮るのが理想です。持ち上げる場合は一回手を濡らしてからお願いします。
休日の後など結構死んで沈んだ魚を見かけます。
釣りマナーより魚の扱いが悪い方、慣れていない方も目立ちます。みんなで魚に優しくしましょうね。
乾いた石の上に乗せて撮影している人をよく見かけますが、バーブレスフックを使用していても、それをやったのでは意味がありません。
魚の皮膚の傷は、フックより強烈で致命傷になります。
リリースした魚は生き延びて産卵しているのも毎年確認されています。
そればかりか、稚魚もちゃんと浮上します。
 俳優の國村隼さんもイワナを。
俳優の國村隼さんもイワナを。
そしてたまに奥多摩湖から遡上した、スーパーイワナも釣れています。
なぜかサクラマス(ヤマメの降海型)とテツガシラ(ニジマスの降海型)の話は聞きませんね。
 夏ならサンダル履きでも楽しめる小菅CR。
夏ならサンダル履きでも楽しめる小菅CR。
C&Rばかり有名になっていますが、小菅川の上流もヤマメが多いので、慣れた人ならこちらのほうが楽しいかもしれません。


沢(支流)
あんまり教えたくありませんが、、、。

多摩川の上流、奥多摩といわれるエリアにはたくさんの支流があり、そのどれもにヤマメ、あるいはイワナが生息しています。


どこの沢、と指定すると、そこに人が集中してはいけませんからあえて名前は言わないでおきます。
地図を見て、ここぞを思う沢へどうぞ。
ただし、道路に車を止める際は他の車の迷惑にならないようにしましょう。


 こんないい風景の中で癒されたいですね。
こんないい風景の中で癒されたいですね。
多摩川の上流は、「魚影が薄い」「人が多い」、と言うイメージが強く、「行っても釣れない。」と多くの方が思っています。ですから、その逆説で、「釣れちゃう。」のです。
ただし、誰でも簡単にと言うわけには行きません。初心者はボウズ覚悟で来てください。ただし景色は抜群です。「これが多摩川か?」ときっと驚くことでしょう。そんな癒しは十分あります。




本流
3月の第一に日曜日に大量放流し、正午に解禁するプット&テイクの川です。放流場所には朝から場所取りする人が多くいます。その場所で解禁日はフライは流せないのでは、、、。

4月に入ってからライズするヤマメを狙うのが面白いかと思いますが、、、、。
ヤマメは真夏でも釣れてるみたいです。

東青梅駅から近い、千ヶ瀬に川よし釣具店というこのエリアでは唯一フライに詳しい店がありますから、リアル情報はそこで聞いてください。
管理釣り場
多摩川の流域には有名○○国際マス釣り場がたくさんあります。
フライフィッシングの受け入れができているとお勧めできるのは以下の釣り場です。
奥多摩フィッシングセンター
多摩川本流に設置されたダイナミックな釣り場。

東京トラウトカントリー
支流の日原川にあるこの釣り場をルアーフライテンカラエリアにしたのは、あのテンカラつりの鬼才、堀江渓愚さん(故人)です。
 渓流をそのまま利用した釣り場。
渓流をそのまま利用した釣り場。
 ヒップウエイダーが欲しいトラカン。
ヒップウエイダーが欲しいトラカン。
 巨石が累々とある中での本格的渓流釣りが。
巨石が累々とある中での本格的渓流釣りが。
小菅トラウトガーデン
奥多摩湖の上流小菅川のほとりにこじんまりとあります。ここのオーナーは小菅川の漁業組合長,古菅一芳さんです。養魚池のような魚影にはシビレます。
 養魚場よりたくさん泳いでます。
養魚場よりたくさん泳いでます。

小菅フィッシングビレッジ
小菅川の中程、小菅村の中心部に設定された村営釣り場。街中を流れるのでそれまでの緑に囲まれた小菅川のイメージと異なりますが、初心者には良いかも。

養沢川フライフィッシングエリア
支流の秋川のさらに支流の養沢川にあります。自然をそのまま利用した4km区間は、非常に魚影が濃いですが、みんな賢い魚たちばかり。
秋川国際マス釣り場の上流に位置しています。お間違いなく。

他の釣り場ではルアーはOKでもフライ禁止もありますからご確認ください。
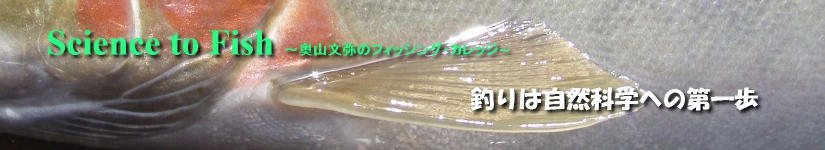
 HOME
HOME 日本のサケ釣り
日本のサケ釣り ウエイダー
ウエイダー